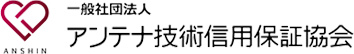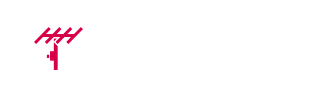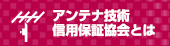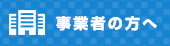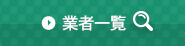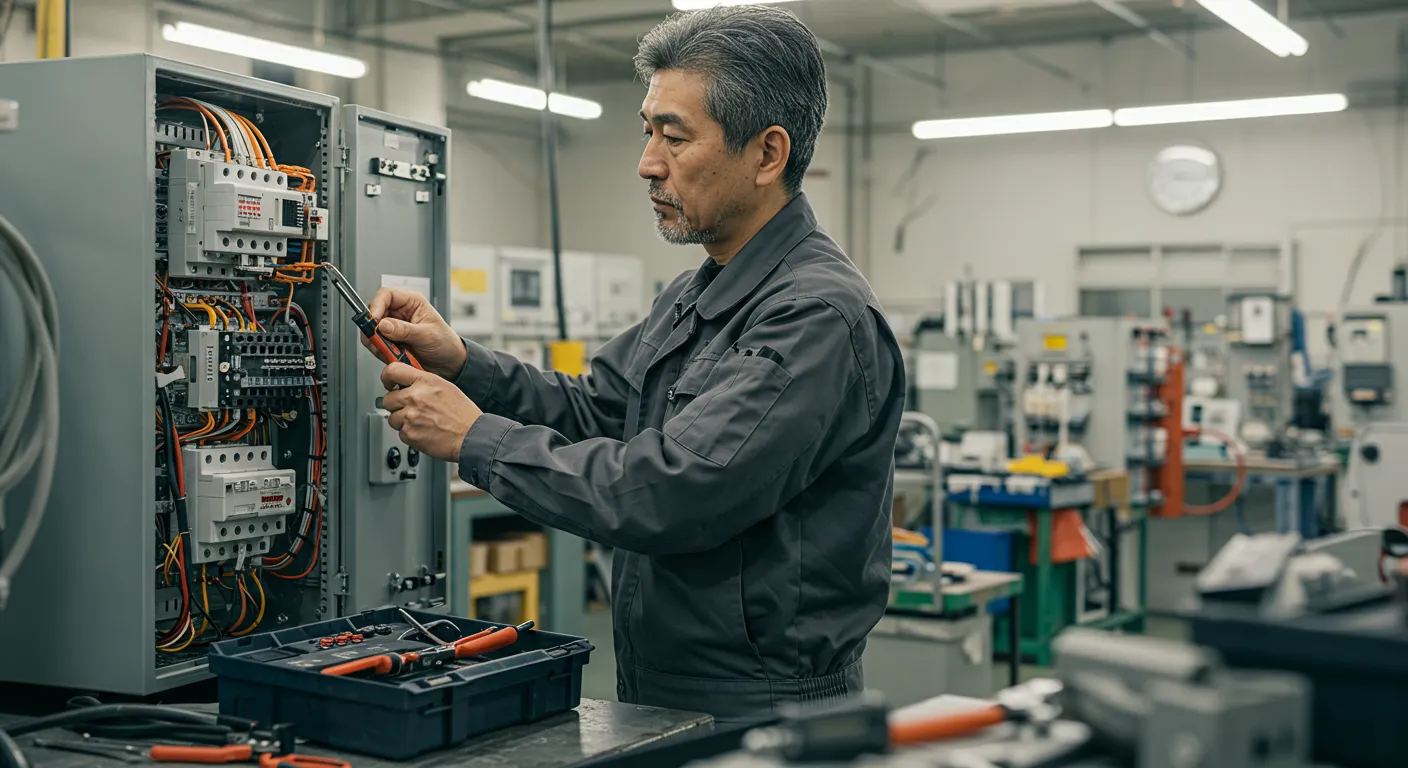
「求人を出しても、まったく応募が来ない…」
「ベテランばかりで、若手が育っていない…」
人手不足が常態化する電気工事業界。2025年6月現在、有効求人倍率は約3倍となり、技術者の平均年齢は高齢化が進むなど、その深刻さは増すばかりです。
しかし、嘆いてばかりではいられません。この構造的な課題は、裏を返せば「人材を確保し、育てられる会社」が圧倒的に有利になるチャンスでもあります。
本記事では、最新の統計データと現場の声をもとに人手不足の根本原因を5つの側面から分解。その上で、明日から実践できる7つの具体的な解決策を提示します。採用、育成、生産性向上を同時に実現し、この人材難時代を勝ち抜くための羅針盤としてご活用ください。
1. 電気工事士不足の現状と、数字で見る5つの原因
なぜ、これほどまでに人手不足が深刻なのでしょうか。経済産業省や業界団体のデータを基に、5つの要因を見ていきましょう。
- 深刻な高齢化と若年層の入職者減
電気工事士を含む建設業全体で高齢化が進行しており、60歳以上が25.7%、29歳以下が約12%(2021年時点・建設技能者全体)とも言われています。
(参照:https://www.shoden-k.jp/blog/column/165046) - 「きつい・汚い・危険」というイメージ
いわゆる3Kのイメージが根強く、若年層、特に女性から敬遠されがちです。実際には空調完備の屋内作業も多いものの、旧来のイメージが採用の大きな障壁となっています。 - 2024年問題(働き方改革関連法)の影響
2024年4月から建設業にも適用された時間外労働の上限規制により、一人の技術者が対応できる業務量が物理的に減少。従来通りの工期・人員では、現場が回らなくなっています。 - 旺盛な建設投資と再エネ需要の拡大
インフラの老朽化対策や都市の再開発に加え、太陽光発電やEV充電設備といった脱炭素関連の工事需要が急増。仕事の「量」が技術者の「数」の増加ペースをはるかに上回っているのが現状です。 - 求められる技術の高度化・多様化
スマートホーム、IoT、BIM(※)など、電気工事士に求められるスキルは年々高度化・多様化しています。従来の技術だけでは対応できない案件が増え、スキルを持つ人材の奪い合いが激化しています。
※BIM: Building Information Modelingの略。3次元のデジタルモデルに、コストや仕上げなどの情報を追加したデータベースを持たせ、設計から施工、維持管理までを一貫して効率化する仕組み。
【打ち手①】採用チャネル拡大(SNS・専門求人・奨学金型採用)
待ちの姿勢では、人材は獲得できません。採用のチャネルを多様化させ、攻めの採用を展開しましょう。
- SNS採用: InstagramやTikTokで、若手社員や女性技術者が活躍する姿、クリーンな作業環境などを発信。会社のリアルな魅力を伝え、採用に繋げます。
- 専門求人サイト: 建設・電気工事分野に特化した求人サイトを活用。経験者や有資格者など、質の高い母集団にアプローチできます。
- 奨学金返済支援モデル: 工業高校や専門学校と連携し、入社を条件に奨学金の返済を会社が支援する制度。学ぶ意欲の高い若手を早期に確保できます。
【成功事例:B電工様】
地元の工業高校と提携し「奨学金型採用」を導入。在学中からインターンとして受け入れ、卒業後、第一種電気工事士の資格取得費用と奨学金返済の一部(150万円)を支援。結果、毎年2名の新卒を安定的に確保できるように。
【打ち手②】多様な人材の活用(女性・シニア・外国人材)
若手男性だけに固執していては、人手不足は解消しません。多様な人材が活躍できる環境整備が急務です。
| 対象人材 | 活用メリット | 受け入れのポイント・法規制 | 活用できる助成金(例) |
|---|---|---|---|
| 女性 | 細やかな作業、施主との円滑なコミュニケーション | 更衣室・トイレの整備、軽量工具の導入、柔軟な勤務体系 | トライアル雇用助成金 |
| シニア | 豊富な経験と技能の伝承 | 短時間勤務、若手の指導役など体力的負担の少ない役割 | 65歳超雇用推進助成金 |
| 外国人材 | 労働力の確保、組織の活性化 | 在留資格「特定技能」の理解、生活・言語サポート体制の構築 | 人材確保等支援助成金 |
特に在留資格「特定技能」は、一定の専門性・技能を持つ外国人を即戦力として受け入れられる制度であり、活用しない手はありません。
【打ち手③】電工DXツール導入で生産性を2倍に
「人がいないなら、一人あたりの生産性を上げるしかない」。DX(デジタルトランスフォーメーション)は、その最も有効な手段です。
- 3Dレーザースキャナー: 現状の建物を数分で3次元データ化。手作業での採寸・図面起こしの手間を90%以上削減。
- BIM/CIM対応CAD: 設計から施工、材料拾いまでを3Dモデルで一元管理。手戻りや拾い漏れを防ぎ、積算精度を大幅に向上させます。
- 遠隔支援ウェアラブルカメラ: スマートグラスを装着した若手作業員の視点を、事務所のベテランがリアルタイムで共有。遠隔地から的確な指示を出すことで、一人で複数の現場を管理できます。
ROI(投資対効果)の目安:
ウェアラブルカメラ(初期投資50万円)を導入し、ベテラン技術者1名の移動時間を1日2時間削減できた場合、人件費と交通費で年間100万円以上のコスト削減効果が見込め、約半年で投資を回収できます。
【打ち手④】教育・資格取得支援の仕組み化
未経験者を採用しても、育てる仕組みがなければ定着しません。OJTとOff-JT(研修)を組み合わせた育成フローを構築しましょう。
【ハイブリッド育成フロー例】
- 入社~3ヶ月: 安全教育、工具の使い方、先輩との現場同行(OJT)
- 4ヶ月~1年: 第二種電気工事士の資格取得支援(外部講習の費用負担、社内勉強会)
- 2年目~: より専門的な研修(高圧ケーブル、シーケンス制御など)への参加支援
- 5年目~: 第一種電気工事士、施工管理技士への挑戦を推奨。資格手当で還元。
「育ててから辞められたら…」と躊躇するのではなく、「育てなければ、会社に未来はない」という発想の転換が必要です。
【打ち手⑤】報酬・キャリアパスの再設計
「この会社で頑張れば、将来こうなれる」という明確な道筋を示すことが、離職防止とモチベーション向上に繋がります。
- 技能等級別モデル賃金表の作成: 「見習い」「一般工」「職長」など等級を設定し、等級ごとの給与レンジと昇格要件(保有資格、対応可能業務など)を明文化。
- 成果連動給の導入: 基本給に加え、担当した案件の利益や顧客評価に応じてインセンティブを支給。頑張りが正当に報われる体系を構築します。
【打ち手⑥】事業承継・M&Aによる規模拡大
自社での採用・育成が追いつかない場合、M&A(企業の買収・合併)も有力な選択肢です。
後継者不足に悩む小規模な電気工事会社は全国に数多く存在します。そうした会社を友好的に買収することで、経験豊富な技術者と既存の顧客基盤を一度に獲得し、対応エリアや事業規模を一気に拡大できます。買収相場は、企業の純資産に年間の営業利益の3~5年分を加えた額が一般的です。
【打ち手⑦】案件プラットフォーム/協力業者ネットワーク活用
自社のリソースだけで全ての案件をこなす時代は終わりました。外部との連携で、稼働率を最適化しましょう。
- 案件マッチングプラットフォーム: 繁忙期に人手が足りない、逆に閑散期に仕事がない、といった波を平準化。必要な時に必要なだけ、協力業者や一人親方を探せます。
- 協力業者ネットワークの構築: 日頃から同業他社と良好な関係を築き、お互いに仕事を融通し合える体制を整備。業界全体でリソースを共有する視点が重要です。
9. まとめ:不足時代に勝ち残る電気工事会社の条件
人手不足はもはや“問題”ではなく、事業活動の“前提”です。この厳しい環境で勝ち残るためには、以下の視点が不可欠です。
【人手不足時代を勝ち抜くロードマップ】
- 【STEP1:守りの強化】(即時~)
- まずは離職防止から。労働環境の改善とキャリアパスの明示に着手。
- 低リスクで始められるDXツール(施工管理アプリなど)を導入。
- 【STEP2:攻めへの転換】(~1年)
- 採用チャネルを複数に広げ、多様な人材(女性・シニア等)の受け入れ体制を整備。
- 育成計画を策定し、資格取得支援を制度化する。
- 【STEP3:未来への投資】(1年~)
- BIM導入やM&Aなど、中長期的な視点で大きな投資を検討する。
変化を恐れず、積極的に行動を起こす企業だけが、この人手不足時代を乗り越え、持続的な成長を手にすることができます。