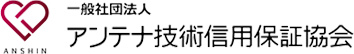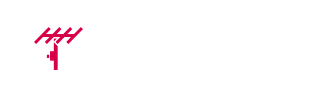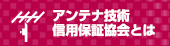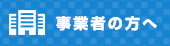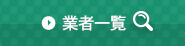「電気通信工事業」と「電気工事業」:その違い、正確に分かりますか?
私たちの生活やビジネスに欠かせない「電気」。しかし、電気に関わる工事と一口に言っても、実は大きく分けて「電気工事業」と「電気通信工事業」という異なる分野があることをご存知でしょうか?
この二つの業種の違いは、扱う対象や目的が異なるだけでなく、建設業許可の要件、必要な国家資格、そして関連する法律まで、様々な点で異なってきます。
この違いを正しく理解することは、
- 建設業許可申請や入札区分で迷っている建設業・工事業の経営者・総務担当者
- 自身のキャリアパスや転職、資格取得を検討している施工管理技士や電気工事士
- LAN工事、防犯カメラ設置、テレビアンテナ設置などの工事を依頼したい発注者
といった、それぞれの立場の方にとって、適切な判断を下すために非常に重要です。
この記事では、「電気工事業」と「電気通信工事業」の定義から、扱う電圧、具体的な工事内容、必要な資格、建設業許可の区分、そしてそれぞれの将来性まで、分かりやすく徹底的に解説します。あなたの疑問を解消し、適切な次のステップへ進むための一助となれば幸いです。
この記事を読むことで、以下のポイントが明確になります。
- 電気工事業と電気通信工事業の基本的な定義
- 扱う「電気」の種類や電圧レベルの違い
- それぞれの業種に含まれる具体的な工事内容・施工事例
- 取得すべき国家資格(電気工事士、工事担任者など)の比較
- 建設業許可の業種区分と専任技術者の要件
- それぞれの分野の将来性やキャリアパス
- 発注者が適切な業者を選ぶためのポイント
まずはそれぞれの「定義」と「概要」を知る
まずは、「電気工事業」と「電気通信工事業」がそれぞれどのような事業を指すのか、基本的な定義を確認しましょう。
電気工事業とは?(主に電力の供給に関わる工事)
電気工事業は、主に建物や設備に電気を「送る」「使う」ための設備に関する工事を指します。電力会社からの電気を引き込み、建物内で使用できるようにするための配線、照明設備、コンセント、分電盤・配電盤の設置などが典型的な工事内容です。
電気工事業は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」や「電気工事士法」などによって regulated されています。これらの法律は、電気工事の安全を確保し、災害発生を防止することを目的としています。
電気通信工事業とは?(主に情報伝達に関わる工事)
一方、電気通信工事業は、建物や設備内で情報や信号を「伝える」ための設備に関する工事を指します。電話設備、インターネット(LAN)設備、テレビ受信設備(アンテナ、ケーブル)、監視カメラ、インターホン、火災報知設備などが含まれます。
電気通信工事業は、「電気通信事業法」や「有線電気通信法」などによって関連付けられています。これらの法律は、電気通信設備の設置や維持管理に関する基準を定めるものです。
【徹底比較】電気通信工事業と電気工事業の「違い」
それぞれの定義を踏まえ、具体的な違いを様々な側面から比較していきましょう。
一番の違いは「工事の目的」と「扱う対象」
両者の最も根本的な違いは、その「目的」と「扱う対象」です。
- 電気工事業: 電力(エネルギー)を供給し、電気機器を動作させることを目的とする。主に電力設備を扱う。
- 電気通信工事業: 情報(信号)を伝達し、通信や監視、情報処理などを行うことを目的とする。主に電気通信設備を扱う。
扱う電圧・電力の違い(弱電 vs 強電)
一般的に、電気工事業は「強電」、電気通信工事業は「弱電」を扱うと言われます。これは、扱う電気の電圧レベルが大きく異なるためです。
弱電・強電の具体的な電圧レベル
明確な定義があるわけではありませんが、一般的には以下のように区分されます。
- 強電: 比較的高い電圧・電流を扱い、動力や照明などに使用される電気(例: AC 100V/200Vなど)。人体に危険を及ぼす可能性が高い。
- 弱電: 比較的低い電圧・電流を扱い、情報信号の伝達などに使用される電気(例: DC 5V/12V、信号レベルの交流など)。感電リスクは低いが、活線作業には注意が必要。
電気工事業では、ビルや工場への動力線引き込み(高圧・特別高圧の場合も)、一般的な家庭用コンセント(100V/200V)などの強電設備が中心です。
一方、電気通信工事業では、電話線、LANケーブル、アンテナケーブル、監視カメラケーブルなど、数十V以下の弱電設備が中心です。
危険度・安全リスクの比較
扱う電圧の違いから、工事に伴う危険度も異なります。
- 電気工事業(強電): 高い電圧を扱うため、感電や火災のリスクが高く、作業には厳重な安全管理と専門知識が不可欠です。
- 電気通信工事業(弱電): 基本的には電圧が低いため、感電リスクは強電に比べて低いですが、電源部の作業や活線作業時には感電の危険性があるため、十分な注意が必要です。
具体的な「仕事内容」・「施工事例」の比較
具体的な工事内容を見ると、その違いがより明確になります。以下は代表的な施工事例です。
| 電気工事業の仕事内容 | 電気通信工事業の仕事内容 |
|---|---|
| 建物の幹線設備工事 | 電話交換設備、端末設備工事 |
| 屋内配線工事(コンセント、照明、スイッチ) | LAN設備(ネットワーク配線)工事 |
| 分電盤・配電盤の設置・改修 | テレビ受信設備(アンテナ設置、配線)工事 |
| 発電設備(太陽光など)の設置・接続 | 監視カメラ・防犯設備工事 |
| 空調設備、給排水設備への電源供給工事 | インターホン、ナースコール設備工事 |
| 道路、トンネル、屋外照明設備工事 | 火災報知設備、非常放送設備工事 |
| EV充電設備の電源工事 | 放送設備、音響設備工事 |
このように、電力を使うための設備の設置・配線が電気工事業、情報や信号を送受信するための設備の設置・配線が電気通信工事業、と区分されます。
例えば、テレビを見るためのアンテナを設置したり、そこから各部屋へケーブルを配線したりする工事は、情報伝達に関わるため「電気通信工事業」に該当します。アンテナ工事の基本的な知識や技術を学びたい方は、当協会の運営する「アンテナ工事の学校」も参考にしていただけます。
必要となる「国家資格」の比較
それぞれの工事を行うために必要となる代表的な国家資格も異なります。
| 電気工事業で主な資格 | 電気通信工事業で主な資格 | 概要 |
|---|---|---|
| 電気工事士(第一種・第二種) | 工事担任者(AI第一種〜第三種、DD第一種〜第三種、総合通信) | 電気通信回線への接続工事に必要な資格 |
| 電気主任技術者 | 電気通信主任技術者 | 電気通信事業者の技術基準の維持に必要な資格 |
| 電気工事士(弱電も一部) | 一部の弱電工事で必要な場合がある |
電気工事業では、一般住宅や店舗などの600V以下で受電する設備の工事には第二種電気工事士、ビルや工場などの最大電力500kW未満の自家用電気工作物の工事には第一種電気工事士が必要です。さらに大規模な設備の保安管理には電気主任技術者が必要になります。
電気通信工事業では、電話回線やインターネット回線を設備に接続する工事(端末設備の接続)には工事担任者、電気通信事業用設備の技術基準の維持には電気通信主任技術者が必要です。
関わる「法律」・「許認可」の違い
前述の通り、関わる主要な法律が異なります。これにより、事業を行う上での登録や許可の体系も区分されます。
- 電気工事業: 主に電気工事業法に基づき、「登録電気工事業者」としての登録が必要です(建設業許可を持っていても、別途「みなし登録」の手続きが必要)。
- 電気通信工事業: 主に電気通信事業法に基づき、「登録電気通信工事業者」としての登録が必要です(建設業許可を持っていても、別途「みなし登録」の手続きが必要)。
建設業許可と登録電気工事業者制度から見る違い
特に事業として本格的に行う場合、建設業許可や各業法に基づく登録が重要になります。ここでも両者の違いがあります。
建設業許可の「電気工事業」と「電気通信工事業」
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために必要な許可です。全部で29業種に分かれており、「電気工事業」と「電気通信工事業」はそれぞれ独立した業種として区分されています。
建設業許可取得の要件
どちらの業種の建設業許可を取得するにも、共通の要件と、業種固有の要件があります。主な要件は以下の通りです。
- 経営業務の管理責任者(経営経験のある人物)がいること
- 専任技術者(請け負う工事に関する専門知識を持つ人物)がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
このうち、**専任技術者の要件**が業種によって異なります。
主任技術者・専任技術者に必要な資格・実務経験の比較
建設業許可において、営業所ごとに置く必要がある「専任技術者」となるためには、原則として以下のいずれかの要件を満たす必要があります。(「主任技術者」もほぼ同等の要件です。)
| 電気工事業 | 電気通信工事業 | 概要 |
|---|---|---|
| 第1種電気工事士 | 技術士(建設部門「電気電子」または「総合技術監理」) | 国家資格保有者(一部資格は実務経験が必要) |
| 第2種電気工事士+実務経験5年 | 第一種電気通信主任技術者 | |
| 電気主任技術者(第1種~第3種)+実務経験5年 | 第二種電気通信主任技術者 | |
| 技術士(建設部門「電気電子」または「総合技術監理」) | 工事担任者(総合通信、AI第一種、DD第一種) | |
| 学歴(指定学科卒)+実務経験3年 | 学歴(指定学科卒)+実務経験3年 | 学歴または実務経験によるルート |
| 実務経験10年 | 実務経験10年 |
電気工事業では電気工事士や電気主任技術者、電気通信工事業では工事担任者や電気通信主任技術者といった、それぞれの専門分野の資格が重視される点が大きな違いです。特に実務経験の年数も要件に関わるため注意が必要です。
「登録電気工事業者」と「登録電気通信工事業者」
建設業許可とは別に、それぞれの業法に基づき、請負で事業を行うには各登録が必要です。
- 登録電気工事業者: 電気工事業法に基づく登録。営業所ごとに主任電気工事士(資格+実務経験)を置くことなどが要件。
- 登録電気通信工事業者: 電気通信事業法に基づく登録。営業所ごとに主任技術者(工事担任者または電気通信主任技術者)を置くことなどが要件。
建設業許可(電気工事業または電気通信工事業)を持っている場合でも、別途これらの登録(みなし登録を含む)が必要となります。
建設業許可(電気・電気通信)取得・登録フロー
建設業許可の取得や電気工事業・電気通信工事業の登録は、それぞれ異なるステップと必要書類があります。具体的な申請の流れや必要書類は、申請先の都道府県や管轄省庁によって異なりますが、一般的には以下の要素を含むプロセスとなります。
(※ここに、申請先(都道府県、経済産業省など)、申請に必要な書類収集・作成、書類提出、審査、登録完了までの主要なステップを図解として表示することを推奨します。視覚的に流れを把握しやすくなります。)
申請に必要な書類や注意点
申請には、申請書本体のほか、登記簿謄本(法人の場合)、住民票(個人の場合)、身分証明書、登記事項証明書、履歴書、健康保険証の写し、そして最も重要な「専任技術者」や「主任電気工事士」・「主任技術者」の資格・実務経験を証明する書類など、多岐にわたります。各都道府県や団体の公式サイトで最新の申請書類様式や手引きを確認することが不可欠です。
それぞれの工事の「将来性」と「キャリアパス」
電気工事業と電気通信工事業は、社会のインフラを支える重要な仕事であり、どちらの分野も将来性があります。ただし、求められる技術や将来の展望には違いがあります。
電気工事業の今後の展望
電気工事業は、再生可能エネルギー(太陽光・風力)の導入拡大、EV(電気自動車)充電インフラの整備、既存建築物の省エネ化や老朽化した電気設備の更新など、今後も安定した需要が見込まれます。特に、新しいエネルギー関連の技術に対応できる人材のニーズは高まるでしょう。
電気通信工事業の今後の展望
電気通信工事業は、5Gの普及、IoT(モノのインターネット)の進化、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に伴うネットワーク環境の高度化、クラウドサービスの普及、セキュリティ対策の強化などにより、今後も拡大が見込まれます。情報通信技術の進歩に合わせて、常に新しい技術を習得していく必要があります。
それぞれの分野で求められる技術・スキル
- 電気工事業: 強電に関する深い知識、安全管理能力、正確な配線・結線技術、図面を読む力、関連法規の理解。
- 電気通信工事業: ネットワークや通信プロトコルに関する知識、配線技術、試験・測定技術、セキュリティ知識、図面を読む力、関連法規の理解。特にアンテナ工事では電波の知識や高所作業の技術が重要になります。
両方の分野で経験を積むことで、対応できる工事の幅が広がり、キャリアの選択肢が増える可能性があります。
【技術者向け】自分はどちらに向いている?
どちらの分野に進むか、あるいはキャリアチェンジを検討する際に、自分の興味や適性を考えてみましょう。
- 物理的なインフラ構築や、高い電圧を扱う仕事に興味がある → 電気工事業
- 情報技術やネットワーク、通信の仕組みに興味がある → 電気通信工事業
- 屋外での作業や、力仕事も多い方が良い → 電気工事業寄り
- 精密な配線や設定、機器の調整などが得意 → 電気通信工事業寄り
- 大規模なインフラを支えることにやりがいを感じる → 電気工事業寄り
- 新しい通信技術やデジタル分野に積極的に関わりたい → 電気通信工事業寄り
これはあくまで傾向ですが、自分がどちらの分野に興味を持ち、どのようなスキルを伸ばしたいかを考えるヒントにしてください。
資格取得・スキルアップのキャリアパス事例
例えば、第二種電気工事士から実務経験を積んで第一種電気工事士を目指すのが電気工事業の一般的なキャリアパスの一つです。さらに電気主任技術者を目指す道もあります。
電気通信工事業では、工事担任者(デジタル・アナログの区分や種別)を取得し、さらに電気通信主任技術者を目指すといったキャリアパスがあります。また、特定の分野(例:ネットワーク、セキュリティ、アンテナなど)の専門性を深めるための民間資格や、メーカー主催の研修などでスキルアップを図ることも重要です。
特に、アンテナ工事に特化した技術やノウハウを習得することは、電気通信工事業での専門性を高める上で非常に有効です。アンテナ工事の学校のような専門機関で学ぶことも、キャリアアップの一つの方法と言えるでしょう。
【発注者向け】どちらの業者に頼むべき?見分け方と選び方
工事を発注する立場の場合、依頼内容によって「電気工事業者」と「電気通信工事業者」のどちらに依頼すべきか判断する必要があります。
依頼したい工事内容で「電気工事業者」か「電気通信工事業者」か判断する
基本的な判断基準は、前述の「仕事内容」・「施工事例」の比較表を参考にしてください。
- 建物のコンセント増設、照明器具の設置、分電盤の交換、エアコン用電源工事など → **電気工事業者**
- オフィス内のLAN配線工事、ビジネスフォンの設置、監視カメラシステムの構築、テレビアンテナの設置・調整 → **電気通信工事業者**
ただし、両方の工事を兼業している業者も多く存在します。確認する際は、その業者が「電気工事業」と「電気通信工事業」の両方の建設業許可や登録を持っているか、または依頼したい工事内容の実績が豊富かを尋ねてみましょう。
信頼できる業者の見分け方・チェックポイント
適切な業者を選ぶためには、以下の点を確認することが重要です。
- 建設業許可・登録の有無:** 依頼する工事の種類に応じた建設業許可や、登録電気工事業者・登録電気通信工事業者の登録を受けているか確認します。
- 国家資格保有者の在籍: 電気工事士や工事担任者など、必要な国家資格を持った技術者が在籍しているか確認します。
- 実績・経験: 依頼したい工事内容に関する十分な実績や経験があるか、過去の施工事例などを確認します。
- 保険加入: 工事中の事故などに備え、賠償責任保険などに加入しているか確認します。
- 見積もりの内容: 見積もり項目が明確で、適正な価格か、追加費用の可能性などについても丁寧に説明があるか確認します。
- 対応: 問い合わせへの対応が丁寧で迅速か、担当者の知識は確かか、契約内容の説明は分かりやすいかなど。
これらのチェックポイントをまとめたリストを作成しておくと、複数の業者を比較検討する際に役立ちます。(※ここに、ダウンロード可能な業者選びチェックリストを提供できる旨を示唆すると、ユーザーにとって利便性が高まります。)
相見積もりを取る際の注意点
複数の業者から相見積もりを取ることは、価格の妥当性を判断し、業者を比較検討する上で有効です。ただし、比較する際は単純な価格だけでなく、工事内容の詳細、使用する材料、保証期間、対応スピード、実績なども含めて総合的に判断しましょう。あまりにも安い見積もりには、手抜き工事や後からの追加費用発生といったリスクも潜んでいる可能性があります。
知っておきたい関連情報・よくある質問(FAQ)
電気工事業と電気通信工事業に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
電気工事業と電気通信工事業を兼業することは可能?
はい、可能です。実際に多くの事業者が両方の業種を兼業しています。ただし、それぞれに必要な建設業許可や、電気工事業法・電気通信事業法に基づく登録をそれぞれ取得(またはみなし登録の手続き)する必要があります。
電気通信工事業で「みなし登録電気工事業者」になれる?(逆は?)
建設業許可の「電気工事業」を持っていれば、「みなし登録電気工事業者」として電気工事業の登録手続きが一部簡略化されます。しかし、建設業許可の「電気通信工事業」だけを持っていても、「みなし登録電気工事業者」にはなれません。同様に、建設業許可の「電気工事業」だけでは、「みなし登録電気通信工事業者」にはなれません。それぞれの業種に対応する建設業許可が必要です。
法改正による影響は?(例:技能実習制度から特定技能への移行など)
建設業界全体に関わる法改正(例:外国人材の受け入れ制度変更、働き方改革関連法など)は、電気工事業、電気通信工事業のどちらにも影響を与えます。常に最新の情報を確認し、適切な労務管理や事業運営を行うことが重要です。特に外国人材雇用に関する制度は近年変更が多い分野です。
関連資格の難易度・勉強時間目安
電気工事士、工事担任者、電気主任技術者などの国家資格は、それぞれ難易度や合格に必要な勉強時間が異なります。一般的に、電気工事士(第二種)は比較的取得しやすく、第一種、工事担任者、電気主任技術者、電気通信主任技術者と難易度が上がっていく傾向があります。詳細な難易度や勉強時間については、各資格の公式サイトや予備校の情報をご確認ください。
事業の安定・拡大を見据える電気工事業・電気通信工事業者の方へ
電気工事業または電気通信工事業として独立された、あるいは今後独立を検討されている皆様にとって、事業を継続し、さらに発展させていくことは大きな目標でしょう。
事業継続に不可欠な「信用力」と「資金調達の安心感」
事業を安定させるためには、継続的な仕事の確保はもちろん、不測の事態への備えや、将来の投資に必要な資金を円滑に調達できる体制が重要です。金融機関との良好な取引関係や、事業としての「信用力」を高めることが、こうした資金調達をスムーズに行う上で不可欠となります。
事業規模に関わらず利用できる可能性のあるサポート
事業規模の大小に関わらず、電気工事業や電気通信工事業を営む事業者の皆様をサポートする様々な制度や団体が存在します。特に、金融機関からの融資を検討する際に利用できる「信用保証制度」は、事業の安定や拡大に必要な資金調達を後押しする重要な仕組みの一つです。
アンテナ技術信用保証協会のご案内
アンテナ技術信用保証協会は、電気工事業や電気通信工事業、そしてアンテナ工事業など、関連事業を営む中小企業の皆様、特に組合員(会員)の皆様の事業安定・発展を支援するための信用保証事業を行っています。
具体的には、組合員の皆様が事業資金(運転資金や設備資金など)の融資を金融機関に申し込む際、協会の保証をご利用いただくことで、金融機関は融資を実行しやすくなります。これにより、組合員の皆様は、単独では十分な融資を受けられない場合でも、必要な資金を調達できる可能性が高まります。
急な経営環境の変化への対応や、将来的な設備投資、新しい技術への対応など、事業継続・拡大には様々な資金需要が発生します。アンテナ技術信用保証協会は、こうした資金面でのサポートを通じて、組合員の皆様が本業に安心して集中できる環境づくりをお手伝いいたします。
まとめ:電気通信工事業と電気工事業の違いを理解し、適切な選択を
この記事では、電気工事業と電気通信工事業の様々な違いについて解説しました。扱う電圧、具体的な工事内容、必要な資格、建設業許可の区分など、多岐にわたる相違点があることをご理解いただけたかと思います。
それぞれの立場(経営者、技術者、発注者)において、これらの違いを正しく理解することは、事業戦略の策定、キャリアパスの選択、そして適切な業者選びのために非常に重要です。
どちらの分野も社会にとって不可欠な役割を担っており、将来性も十分にあります。ご自身の目的に合った分野を選択し、必要な準備と知識・技術の習得を進めていくことが、成功への鍵となります。
もし、特定の分野(特にアンテナ工事を含む電気通信工事など)の専門的なスキルアップや、事業運営に関するお悩みがある場合は、関連する専門機関や支援団体、あるいはアンテナ工事の学校のような事業者をサポートする組織の情報を収集し、必要に応じて相談してみることをお勧めします。